相変わらず日露戦争が続く。明治の昔とはいえ、すでに近代戦である。凄まじく人間が消費されていく。
とりわけひどいがの旅順である。この地を任されたのは乃木希典。有名な人だが、軍事的にはまったくの無能であったらしい。ただし、この戦争における人事は、旧時代からの人物を司令官に据え、近代兵術を修めた新世代の人物を参謀に添えるという体裁を取っており、作戦は基本的に参謀が立てる。乃木の不幸は、その参謀の伊地知までが無能で、かつ頑迷固陋だったことにある。彼らのやることは戦争当時から無益の殺生と言われていたようで、敵も味方も誰もがそれを理解できなかった。
司馬の陸軍に対する嫌悪も随所に顔を出す。彼が本当に嫌いなのは後年の陸軍の愚劣さだろうけど、その悪しき先例をこの時期の陸軍に見出すたび、彼は苦虫を噛み潰さなければ気が済まないのである。
織田信長は桶狭間の奇襲戦法でそのキャリアをスタートさせた。しかしそれが百に一つの成功例であることを知っていたがために、二度と同じことを繰り返しはしなかった。
陸戦における日露戦争は、全体として桶狭間的状況と宿命と要素に満ちているということはすでに触れた。これが、意外に成功した。
それに成功したことでの旨味により、日露戦争後の日本陸軍の体質ができてしまったという滑稽さは、いったいどういうことであろう。
日露戦争における日本陸軍は、砲弾が慢性的に欠乏したり、あるいは機関銃という新兵器をほんのわずかにしか持たなかったという点では欠けたところがあるが、その他の装備では世界第一流の陸軍であったといっていい。
その後、昭和二十年にいたるまでの日本陸軍は、装備の上では二流であり、二流の上になったことすらない。
「日露戦争はあの式で勝った」
とそういう固定観念が、本来軍事専門家であるべき陸軍の高級軍人のあたまを占めつづけた。(p.256-257)
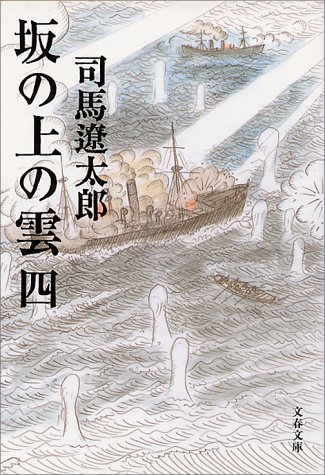
- 作者:司馬 遼太郎
- 発売日: 1999/01/10
- メディア: 文庫